
「いつも、本当によく勉強を頑張っていますよ」 「周りの友達に優しく、頼りになる存在です」
筆者が教員時代には、保護者にこのようなことを伝えると、「信じられない!家ではすごく荒れているんです」と言われることが本当に多々ありました。
教員側である筆者も、いつもニコニコで頑張り屋のこの子がお家で癇癪?と驚いたことは、もう数えきれないほど…。
子どもの癇癪が続くと大変ですよね。子ども自身はもちろん、周りの家族も疲弊してしまいます。
外ではいい子なのに家だけで癇癪を起こす子どもには、どのような理由があるのでしょうか。癇癪を起こす子どもとの接し方や発達障害の可能性まで、元小学校教員の秋野みんみが解説します。
なぜ、外ではいい子なのに家だけで癇癪を起こしてしまうのでしょうか。
癇癪を起こすことを通して、子どもがどのようなSOSを出しているのかを考えることが大切です。
子どもは外で頑張りすぎた反動で癇癪を起こしている場合があります。
例えば、小学校入学時や新学期に新しい環境に馴染もうと頑張りすぎていたり、「外ではいい子にしないといけない」と過剰に気を張っていたりすることが考えられます。
頑張り屋で何事にも一生懸命なことはとても素晴らしいことですよね。しかし、家で癇癪を起こすということは、気持ち的なキャパシティを超えて大きなストレスを抱えている状態の可能性があります。
行き渋りや不登校などに繋がる前に、早めの対応が大切です。
ママ・パパに甘えたいという気持ちが、子どもの癇癪に繋がっている場合もあります。
癇癪はママ・パパなら受け止めてくれる、わがままを聞いてくれるという信頼の表れでもあります。
逆に愛情不足を感じるときに癇癪を起こすこともあるようです。「自分は愛されているのかな?」 という不安から、「ママ・パパに甘えたい」という気持ちが癇癪やわざと手のかかる行動をするなどに繋がることがあります。
とくに低学年のうちは、言いたいことや思いを言葉でうまく説明できないことが、癇癪に繋がる場合があります。「何でわかってくれないの?」「まだやりたかったのに…」そんな思いが伝えられなかったとき、衝動的に癇癪が起こってしまうのです。
子どもはまだまだ感情のコントロールが未熟です。そのため、うまく気持ちが伝えられなかったときには子ども自身もどうしたらいいのか分からないのです。そのモヤモヤが癇癪となって爆発してしまうのですね。
学校でのトラブルが自宅での癇癪につながっている場合があります。
小学校では保育園・幼稚園時代と違い、友達関係が見えにくいことから、気付いたときには子どもが嫌な思いをしていたということも…。
また、家だけで癇癪を起こすタイプの子の多くは、学校ではいい子できちんとしたいと思っている分、ママ・パパが思う以上に些細なことで学校に不満を感じていることがあります。
例えば、
など、ママ・パパから見ると「え?そんなことであなたがイライラする必要ないよ!」と思うようなことも、自分がきちんとしている分許せないと感じてしまうものなのです。
癇癪を起こす子どもに接するのは、わが子であっても辛く感じることもありますよね。 ここでは、家でだけ癇癪を起こす子どもに対する接し方について考えていきましょう。
まずは、子どもの話をとことん聞くことから始めてみましょう。
その際、子どもの話を否定したり遮ったりすることなく、どんな気持ちもしっかりと受け止める姿勢が大切です。「うん、うん。そうだったんだね。それから?」と、どんどん感情を吐き出させることを意識してみましょう。
これは、子どもにアドバイスや指針を与えることではなく、子どもの思いに寄り添い安心感を与えることが目的です。安心感が積み重なり自己肯定感が高まることで、子どもの癇癪が和らいでいくことが期待できます。
子どもが話してくれた感情を、子どもの視点に立って代弁してみましょう。
例えば、
のように、子どもの気持ちに合う言葉で伝えてあげましょう。
子ども自身も感情が整理できますし、自分の気持ちに合う言葉をママ・パパの代弁から学んでいくことで、癇癪を起こさなくても感情を伝えられることに気付いていきます。
ふだんから子どもの表情や声のトーン、仕草などに変化はないか日々観察しましょう。
気になることがある時には、子どもに聞くのはもちろんですが、学校や習い事の先生に様子を伺ってみるのも良いかもしれません。
表情が暗いなと感じたときには、癇癪が起こる前に「何かあった?」と声をかけられるといいですね。話を聞いたあとには、スッキリとした優しい表情になっているかもチェックしたいものです。
このように癇癪ではなく、しっかりと言葉で思いを吐き出させることを繰り返し練習していくことが大切です。
ママ・パパは共感とともに、上のようなオープンクエスチョン(はい、いいえで答えにくく、思いや考えを引き出しやすい質問の仕方)を意識して話を聞くことをおすすめします。
子どもの思いをしっかりと引き出して、「癇癪を起こさなくても、自分は言葉で伝えられる」と子どもにじっくりじっくりと自信をつけてあげたいですね。
癇癪の原因は人それぞれであり、その原因は複数ある場合も…。
その1つとして、子どもが発達障害であるという可能性も考えられます。発達障害だと必ずしも癇癪を起こすというわけではありませんが、発達障害の子どもたちは特性として感性が強い場合が多く、ほんの些細なことでも癇癪やパニックに繋がってしまうことがあります。
激しい癇癪が続き、子ども自身やママ・パパが辛いときには、専門機関に相談してみましょう。各自治体の相談窓口や児童相談所などでは、無料で相談、アドバイスを受けることができます。発達障害の有無を知りたい場合、医療機関の紹介などもしてくれますよ。
***
家での癇癪がひどいと、ママ・パパも心が疲れてしまいますよね。
外で子どもが頑張ることができているのは、家が安心して自分を出せる場所だからなのでしょう。家庭が安心できず、外でそのストレスを発散してしまうよりは健全と言えるのではないでしょうか。
紹介した接し方は、地道に積み重ねていくことが大切です。まずは、話をじっくりと聞くことから挑戦してみましょう。障害の有無に関わらず、ママ・パパの心が疲れてしまったと感じたときには、専門機関に相談してみることも考えてみましょう。
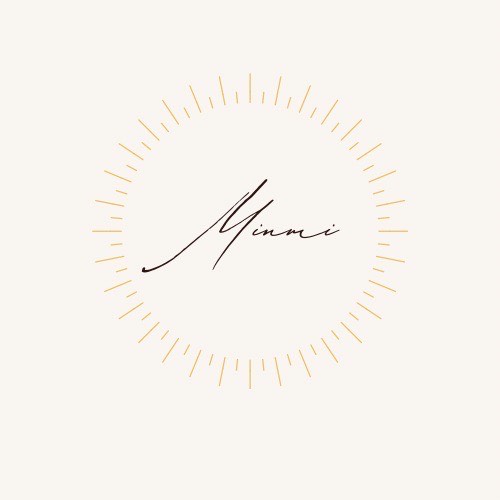
ライター 秋野みんみ
元小学校教員ライター。公立小学校で10年の勤務経験有り。 現在は転勤族の妻で息子の育児に奮闘中!教員経験を生かして、お役に立てる情報を発信してきます♩

愛されている子ども・愛情いっぱいに育てられた子どもの特徴|わが子が出すサイ...
2023.08.13

「大好き」と言われて育った子の特徴は?今からできる「満たされた子」に育てる...
2023.09.19

思い通りにならないと怒るのはなぜ? 3歳・4歳・5歳が癇癪を起こす理由と保...
2023.05.10

「早く食べなさい」は逆効果!【食べるのが遅い子ども】に毎食イライラしていま...
2021.02.25

3人目の子育ては大変?先輩ママに聞く3人育児の大変さと嬉しさ
2022.12.19
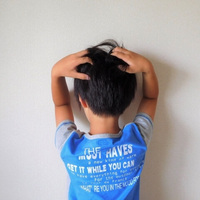
小学生が家でだけ癇癪を起こす理由は?発達障害の可能性もある?「外ではいい子...
2023.08.10
パパっ子になるのはママの愛情不足が原因?ママ嫌いに見えてしまう理由やパパっ...
2023.08.24

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.02.14

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

5歳の平均睡眠時間は?昼寝はしないほうが良い?5歳児の睡眠事情をアンケート
2023.03.16