

「何もしてないのに先生から怒られた!」
わが子からそんな話を聞いた時、みなさんならどうしますか?
そのまま感情的に電話をして先生に問いただす…なんてことをしてしまうと『モンスターペアレント』と呼ばれてしまうかもしれません。だからと言って、モンスターペアレントと思われたくないから、モヤモヤするけど泣き寝入りするというのも学校への不信感が募るだけですよね。
モンスターペアレントとは、実際にはどんな人のことを言うのでしょうか?
元小学校教員ライターの秋野みんみが、実際に教員時代に体験したモンスターペアレントの事例や特徴、モンスターペアレントにならないためのポイントを徹底解説します。
 モンスターペアレントという言葉が使われるようになったのは2007年頃からのことです。
モンスターペアレントという言葉が使われるようになったのは2007年頃からのことです。
元・小学校教諭で教育技術を提唱するTOSS代表の向山洋一氏により「不当、不可解な要求を、次々に担任、校長、学校につきつけている保護者」のことをモンスターペアレントと定義付けられました。
ドラマのテーマとして扱われたりニュースで報道されたりしたことから、今ではすっかり定着している言葉です。
具体的には、以下のような特徴が挙げられます。
学校としてもできる限り、保護者の思いに寄り添いたいと思っているのです。
それでは、モンスターペアレントと言われてしまうのは一体どのような事例なのでしょうか。
実際に教員時代に私が体験したり聞いたりした事例をいくつか紹介します。
 クラスで学活の時間を使ってお楽しみ会を計画した時のことです。
クラスで学活の時間を使ってお楽しみ会を計画した時のことです。
学活は毎週水曜日の1時間目に行っていたため、来週の水曜日の1時間目にお楽しみ会をすることが決まりました。
その日の放課後に、とある保護者から電話がかかってきました。
「来週の水曜日は習い事の都合で学校を休むため、うちの子がお楽しみ会に出られないと悲しんでいる。お楽しみ会を違う日に替えてほしい」
もちろん習い事の都合で欠席する子どものためにお楽しみ会を違う日に替えることはできないので、ていねいにお断りしました。
私用で欠席するにもかかわらず、クラス全体に関わる日程を変更してほしいというのは理不尽であり、対応することは難しいです。こんなこと言う人いるの?と思うかもしれませんが、意外とよく聞く話です。
 高学年のマラソン大会でのことです。
高学年のマラソン大会でのことです。
トップを争っていた2人のうち1人が途中で靴が脱げてしまい、履き直している間に数人に抜かされてしまい順位がだいぶ落ちてしまいました。
その子は泣いていたものの、周りから励まされて自分の順位に納得していましたが、観覧していた親が感情的な様子で担任のもとへ…。
「途中で靴が脱げなかったら1位になれていたはず。靴が脱げないように靴紐をきつく縛ったか、うちの子の様子を確認したんですか?」
靴が脱げないように靴ひもについて声をかけることはもちろん行いますが、一人一人の靴紐がきつく縛られているかを確認することはできません。その場ではまず保護者のわが子を思う気持ちに共感してなだめるしかありませんでした。
一人一人の靴ひもをチェックすることが難しいのはもちろんですが、高学年という多感な時期に保護者が担任に対して怒っている様子をみたその子は、「あれって〇〇のお母さんだよね?」と周りの友達に言われたことがとても恥ずかしかったそうです。
保護者の感情的な行動は、子どもの学校生活に悪影響を与える可能性が大いにあります。
 春休み前に、クラス替えについて保護者から連絡帳にお手紙がありました。
春休み前に、クラス替えについて保護者から連絡帳にお手紙がありました。
「うちの子はやんちゃな子が苦手なようです。この子達と一緒のクラスになった場合、うちの子は学校に行かせません。」という文章と共に、10人ほどの名前が書いてあり驚いてしまいました。
クラス替えの際に参考にはしますが、すべてを叶えることは難しいですということをお返事しましたが、納得いかなかったようで夕方に電話がかかってくることが続きました。
この事例はいかなる場合でもモンスターペアレントと認定されてしまうわけではありません。
けんかが多く相性が悪かったり過去にトラブルがあったりしたなど、保護者だけでなく教師側から見てもクラスを離した方がいいという場合には、クラスを離すことを検討する場合もあります。
心配なことは分かりますが、いろいろな人と関わる中で子どもは成長していきます。「うちの子ならどんなクラスでも大丈夫!」と信じて見守る気持ちも大切です。
 仕事で朝早く家を出るという保護者から、このような電話がありました。
仕事で朝早く家を出るという保護者から、このような電話がありました。
「朝、子どもを家に置いて仕事にいくのは心配なので、学校に7時に行かせたい。
教室で担任の先生と一緒に待たせてほしい。」
多くの学校で校門が開くのは8時前後で、それまでは安全に配慮して教室に入ることができないようになっていることがほとんどです。
心配な気持ちは分かりますが、GPSやキッズケータイを所持させることをおすすめしてお断りしました。
担任の先生にも子どもを保育園に送ってから学校に向かうなど、家庭の事情があります。
学校で決められた時間以前に登校させて先生に教室で見てもらえるのなら、そうしたいと考える保護者はほかにもいることでしょう。安全上においても、この子だけを特別扱いはできません。
先生たちは早く学校に来ているし少しくらいいいのでは?と思う方もいるかもしれませんが、多くの自治体では先生の勤務開始は8時半前後からです 。 子ども達の登校時間が勤務開始よりも早いため、先生たちは朝の時間は無償で働いています。
 ある日の放課後、F君の保護者から強い口調でこのような電話がありました。
ある日の放課後、F君の保護者から強い口調でこのような電話がありました。
「今日の家庭科の授業で、家庭科のA先生から怒られて納得していないようなのですが、 うちの子はなぜ怒られたのでしょうか?A先生から直接話を聞きたいのですが、代わってもらえませんか?」とのことでした。
しかし、この日は家庭科の授業はなく、A先生からもF君を指導したという話は聞いたことがありませんでした。次の日、F君に状況を聞いてみるとまったくの嘘だったことが分かりました。理由はお母さんが弟の話ばかりするから、注目を浴びたかったというものです。
保護者からは、「思春期に入りかけているF君よりも年下の弟を可愛がっていた気がします。申し訳ありません」と謝罪されました。
このようにわが子の話だけを鵜呑みにして、正確性を問わず、感情的に電話をしてくるというケースは非常に多く見られます。
受けた先生としても勘違いだったと謝罪をされたとはいえ、気持ちの良いものではないでしょう。
同じクラスのママ友から話を聞いてみたり、子どもの話をもう少し深堀して信憑性を確認したりしてから連絡をすることが大切です。
学校での子どもの様子はすべてを知ることができませんから、様々な面で不安を感じることは当然のことです。
特に新1年生の保護者の方においては、幼稚園や保育園の頃と比べて先生と話をする機会や子どもの様子を知る機会が極端に減るケースが多いので、戸惑ってしまうという話もよく聞かれます。
学校に子どものことで要望や相談をする際、どのような対応をすればモンスターペアレントとならなくて済むのでしょうか?
ここでは、5つの気をつけるべきポイントを紹介します。
学校に連絡をする前に、まずは自分たちに非はないかどうかをふり返ってみましょう。
子どもが何かトラブルを起こしてしまった時に、「うちの子は家では本当に良い子で、こんなことをするのは信じられない。学校が悪い!」とすべてを学校のせいにする保護者をこれまで何度も見てきました。
まずは何かを学校に伝える前に、一度冷静になり自分の子どもや保護者自身に非がなかったかをふり返ることが大切です。幼少期の問題行動は、家庭環境に原因があることも多いです。例えば、家族から目を向けてもらえていないと感じる子どもが、注目を浴びるために学校の備品をわざと壊すなどの事例はよくあることです。
起こった出来事だけを見て勢いで学校に連絡するということは、学校に通う子どもにとっても悪影響を及ぼす可能性があるため、気を付けるようにしましょう。
 伝えたいことが自分の子どものことだけを考えた自己中心的な事項でないかをふり返ってみましょう。
伝えたいことが自分の子どものことだけを考えた自己中心的な事項でないかをふり返ってみましょう。
わが子が良い思いをしてほしいという親心は分かりますが、学校は集団生活を学ぶところ
ですから、1人の子どもを特別扱いするような主張を通すことは難しいでしょう。
 一方的に主張するばかりではなく、相手の意見をしっかりと聞くようにしましょう。
一方的に主張するばかりではなく、相手の意見をしっかりと聞くようにしましょう。
トラブルが起きた場合には相手の保護者の思い、学校への要望であれば先生の考えをしっかりと聞き、折り合いをつけようと努力することが大切です。
感情的に自分の主張だけを通そうとする姿はあまりにも冷静さに欠けますし、相手側としても意見に耳を傾けてくれる方が、少しでも主張を受け止めようと努力してくれるものです。
 子どもの意見だけで物事を判断することはやめましょう。
子どもの意見だけで物事を判断することはやめましょう。
先ほど事例(5)でも紹介したように、子どもは勘違いや見間違え、子どもにとって不利なことを隠して話している場合があります。
先生に伝えようか迷ったときには、同じ学校のママ友に意見を聞くのも良いでしょう。 ママ友との交流をある程度広げておくことで、学校の情報が先生や子どもからだけでなく ママ友からも入ってくるので、広い視野で物事を考えることができます。
 子どもが悲しそうな顔で帰宅すると心配になりますし、親としてはできるなら解決してあげたいと根掘り葉掘り聞きたくなるものです。
子どもが悲しそうな顔で帰宅すると心配になりますし、親としてはできるなら解決してあげたいと根掘り葉掘り聞きたくなるものです。
学校では集団生活を通してさまざまなことを学んでいきますから、日々ケンカやトラブルが起こります。いじめは許されることではありませんが、日頃の些細なケンカであれば解決していく過程で成長していくことも多くあるのです。1位になれなくて悔しかった思いや、忘れ物をして注意されて反省したことも、すべては子どもの『成長のタネ』となります。
保護者が介入しすぎたことで幼少期に成長の機会が少なかった子どもは、社会人になって親から離れたときに、自分で問題を解決することが難しくなる場合があります。親が介入する・しないのボーダーラインを見極め、大きな問題でなければある程度距離を保ち見守ることも必要でしょう。
***
モンスターペアレントの具体例やならないためのポイントについて紹介しました。
現場にいる学校の先生たちは保護者の思いをできるだけ受け止めたいと思っています。
しかし、多くの子どもたちを1人で担任している先生にとって、現実的に個々に配慮できることには限界がありますから、「本当にこれは学校にお願いすることかな?」と立ち止まってみることも大切です。
また、先生に何かを伝えるときには、子どもが聞いていても恥ずかしくない口調で、1人の大人として冷静な態度で臨むようにしましょう。 親のモンスターペアレントになってしまったことで、子どもが学校で過ごしづらくなるというのは良くある話です。
今回の記事が、モンスターペアレントと思われることなく、学校と円滑に繋がっていくために参考になれば幸いです。
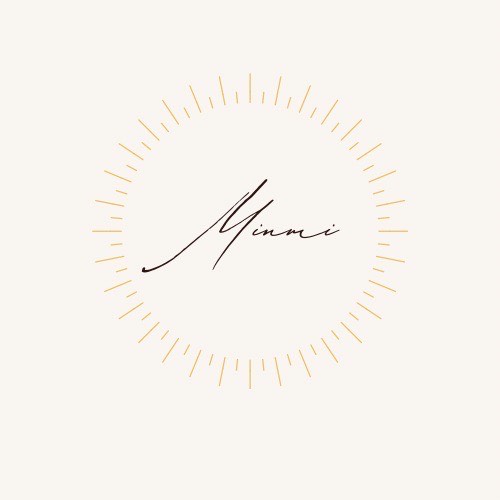
ライター 秋野みんみ
元小学校教員ライター。公立小学校で10年の勤務経験有り。 現在は転勤族の妻で息子の育児に奮闘中!教員経験を生かして、お役に立てる情報を発信してきます♩

【2023年】小学校の夏休みはいつから?都道府県別の夏休み期間を一覧でチェック
2023.03.06

ママの「運動会コーデ」30代、40代やぽっちゃりママのリアルコーデ!プチプ...
2023.04.16

小学生女子に人気のファッションブランド・通販サイト13選|おしゃれな服をG...
2023.03.17

「上履き洗い」結局何が一番ラクでキレイに?各種洗剤・洗濯機用ネット・電動ブ...
2021.12.25

【セリア・ダイソー・キャンドゥ】100均メッシュバッグ使い比べレポ!外遊び...
2023.04.28

不器用でも大丈夫!忙しい朝の簡単「登園ヘアアレンジ」子どもからの「かわいい...
2022.04.09

【ダイソー】ようやく入手可能に!大バズリした「すべり止め液」は子どもの靴下...
2023.03.21

【ダイソー&セリア】何枚も何枚も買いたくなる♪100均「ネットケース」が"...
2021.06.17
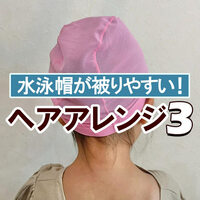
ヘアピンなしでも崩れにくい!水泳帽が被りやすい【子どものプールヘア3選】帽...
2022.07.15

不器用ママでもOK!ヘアピン不要&帽子もかぶれる【登園ヘア】運動会練習でも...
2022.05.09